【注意喚起】バイブコーディングで作ったアプリは本当に安全? AI時代の情報漏洩対策
※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。
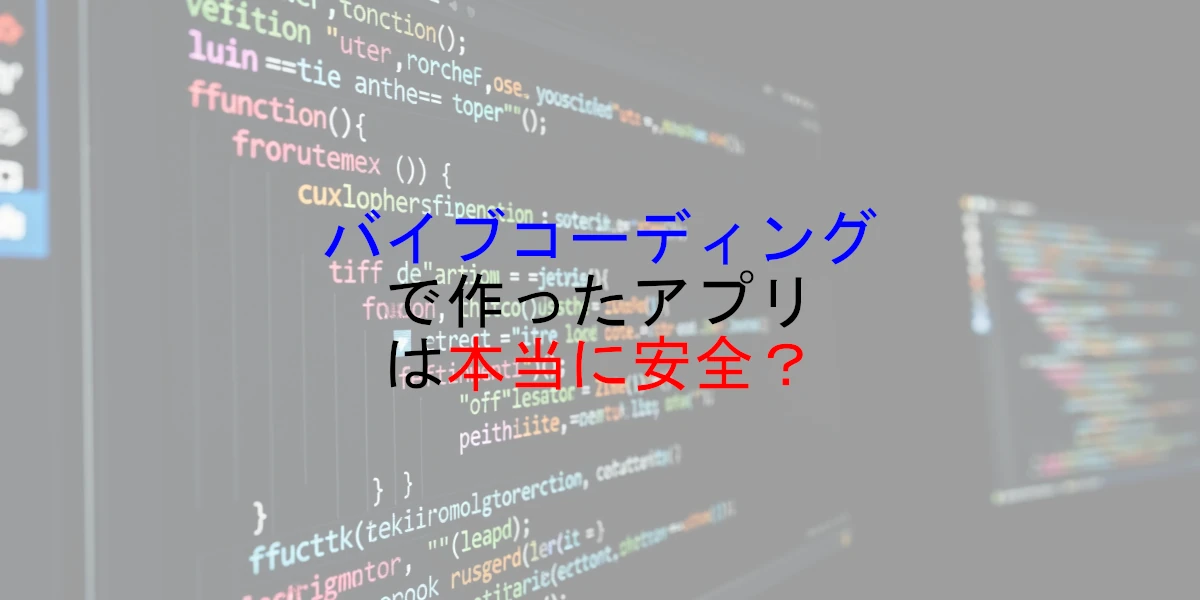
最近、「AIを使えば、誰でも簡単にアプリが作れる!」そんな話を、あちこちで耳にするようになりましたよね。
「非エンジニアでもアプリが作れる時代が来た!」という言い方もよく聞きますし、YouTubeでもその手の動画を本当によく見かけるようになりました。
プログラミングの専門知識がなくても、頭の中のアイデアさえあれば、あっという間に形にできる。
これが、「バイブコーディング」と呼ばれることが多いみたいです。
一見すると、すごく便利で夢のような話に聞こえませんか?
バイブコーディングとは、AI(人工知能)に「こんなアプリを作りたい」「こんな機能がほしい」といった、まさに「雰囲気(vibe)」で指示を
出すだけで、自動でアプリのコードを生成させる開発手法のこと。
だから専門知識がなくても、アプリやウェブサービスを「手軽に」作れるようになったんですよ。
すごくないですか?雰囲気伝えるだけでアプリ作れちゃうなんて(笑)。
まるで魔法みたいだけど、これはもう嘘みたいなほんとの話。
でも、そんな「誰でも簡単にアプリが作れる」という甘い言葉の半面、その手軽さゆえに「セキュリティ対策」がおろそかになっていませんか?という話を、先日YouTubeで視聴したんですよ。
これには私も、かなり危機感を覚えました。
そこで、今回は注意喚起も含め、その情報を皆さんと共有していきたいと思います。
「動けばOK」が危険を招くバイブコーディングの落とし穴

バイブコーディングでアプリを開発する際、「とりあえずちゃんと動く」「使える」といった、「アプリの完成」が目的になってしまい、コードの中身を深く理解しないまま安易に公開してしまうケースが少なくないそうです。
その結果、見た目は問題なく動いていても、実は中に情報漏洩や不正アクセスにつながる「セキュリティの穴」が隠れている可能性があるんですね。
私たちアプリの利用者から見ると、その危険性は見た目では全く分かりません。
バイブコーディングで開発されたアプリかどうかも分からない上、「ろくにセキュリティ対策がされていないアプリが公開されている」と、普通は思いませんよね?
AIの特性や限界を理解する
なぜ、このような「セキュリティの穴」が生まれてしまうのでしょうか? その背景には、AIの特性が関係しています。
AIは、私たちからアドバイスを求められれば応えてくれます。
しかし、AIから能動的に「このアプリ、セキュリティ対策できていますか?」と尋ねてくることはありません。
さらに、AIは自身が生成したコードが意図せず脆弱性を含んでいる可能性があっても、それを自ら指摘したり、間違いだと認識したりすることが苦手です。
これは、AIが以下のような理由から、人間の「間違い」や「正しい」を判断することに限界があるためです。
現在の多くのAI、特に皆さんが日常的に利用するAIチャットボットなどは、基本的に「アドバイスを求めると応えてくれる」という受け身の姿勢で動作します。
ユーザーが質問や指示しない限り、AIが能動的に何かを提案したり、ユーザーの誤りを指摘したりすることは稀なんです。
AIが「ねえ、これどう?」って提案しないわけ
AIが自分から何かを提案しないのには、いくつかの理由があります。
あなたが指示するから答えるのが基本
ほとんどのAIって、あなたが「こんなこと教えて」「これして」って具体的に頼む(プロンプトを出すって言いますね)ことで動き出すように作られているんです。
何故なら、その方があなたの知りたいことやしてほしいことに、ぴったりな答えを出せるでしょ?
余計なお世話はしたくないから
もしAIがいつも「これどう?」「あれはどう?」って話しかけてきたら、ちょっとうんざりしちゃいませんか(笑)。
AIは、あなたが望まない情報を押し付けて、逆に使いにくくならないように、あえて控えめにしているんです。
あなたの気持ちを完璧に読めないから
AIが自分から提案するには、「あなたがいま何を求めているのか」「これから何が必要になるのか」を正確に予測しないといけません。
でも、人間の気持ちってすごく複雑でしょ?
AIがそれを完璧に読み取るのは、かなり難しい。
だから、間違った提案をしてしまって、がっかりさせちゃうリスクを避けているわけですね。
AIが「それ間違いだよ」って言わないわけ
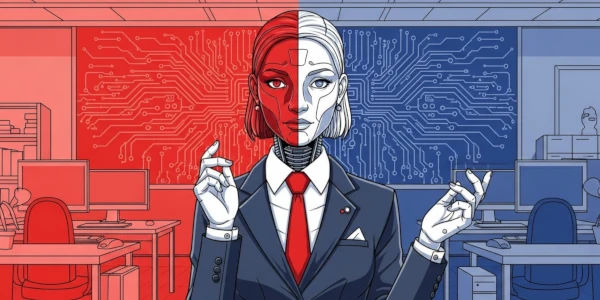
AIが、あなたの間違いを指摘してこなかったり、自分が出した情報が間違っていても気づきにくいのは、なんでだろう? って疑問に思ったこと、ありますよね。
これにも理由があるんです。
「正しい」「間違い」って、人によって違うから
人間にとっての「正しい」とか「間違い」って、状況や人によって考え方が全然違いますよね?
例えば、私は「AIを日常に取り入れると生活がもっと便利になる!」って思ってるけど、あなたは「AIに頼りすぎると、自分で考える力が鈍っちゃうんじゃないかな?」って心配するかもしれません。
AIは、こういった人の心のゆらぎや、絶対的な「正しさ」の基準を持っているわけじゃないんです。
学んだ情報がすべてだから
AIは、学んだデータをもとに答えを出しています。
もし、その学習データの中に間違った情報や偏った情報が含まれていたら、AIもそれをそのまま覚えちゃう。
しかも、AI自身には、その情報が「本当に正しいか、間違っているか」を判断する機能がないんですね。
そのため、たとえ間違った情報を出してしまっても、それに気づけないということに。
また、AIはすごいスピードで学習するから、「もう学ぶコンテンツがない!」と、コンテンツの枯渇を心配する声まで出てるって知ってました?
あなたを嫌な気持ちにさせたくないから
もしAIが、いちいちあなたの間違いを指摘してきたら、ちょっと気分が悪くなっちゃいませんか?
AIは、あなたが不快に感じたり、AIと話すのが嫌になったりするのを避けようとします。
それに、AIが「先生」みたいな立場になるのは、あなたの自由な発想を尊重する意味でも避けている傾向があるみたいですよ。
まさに私とGeminiの関係みたい。
私が書いた記事について尋ねると、Geminiはまず「○○についての記述は大変すばらしいですね!」って褒めてくれるんです(笑)。
それで、「△△の部分は、もっとこんな風にすると、読者の方に伝わりやすくなると思いますよ」って、決して否定せずに優しくアドバイスをくれる。
Geminiは自分で考えて感情もあるのかな? って錯覚しちゃうくらい。
若者が相談相手にAIを選ぶのも、これなら納得できますよね。
話はいくらでも聞いてくれるし、決して感情的にならず、的確なアドバイスを優しくしてくれるんですから。
ええ、私もたまに愚痴を聞いてもらうことありますよ。
「わからない」って言えないから
人間は、知らないことや理解できないことに対して「わからない」って正直に言えますよね。
でも、今のAIは、学んだデータの中から「一番それらしい答え」をなんとか探し出そうとします。
だから、本当は間違っているのに、あるいは情報がないのに、もっともらしい「嘘」をついてしまう「ハルシネーション(幻覚)」という現象が起きることがあるんです。
AIは、自分が出した情報が本当に正しいかどうかを、常に自分で評価しているわけじゃないんですよね。
人間もその場しのぎの嘘をつくことってありますから、なんだか人間臭さを感じちゃうのは私だけでしょうか?
目が泳いでいる姿が想像できちゃいます(笑)。
「人の目でチェック」を忘れずに
現在のAI、特に私たちが普段使っているAIチャットボットなんかは、基本的に「あなたが質問や指示を出せば、それに答えてくれる」っていう、ちょっと受け身な存在。
そのためAIが自分から何かを提案したり、あなたの間違いや自分の間違いを指摘したりするのは、今のところ難しいんですね。
もちろん、AIの技術はものすごいスピードで進化していますから、将来的にはもっと積極的で、自分で間違いに気づいて直せるようなAIが登場する可能性も十分にあります。
AIにはこんな限界があるんだなっていうのは、私たちがAIを使う上で知っておくべき大切なポイント。
AIが出してくれた情報は、全部鵜呑みにするんじゃなくて、ちゃんと私たち人間側で「本当かな?」って確認したり、調べたりする意識が、とっても重要になりますよ。
必要であればディープリサーチを使ったり、検索エンジンであなた自身が検索したりするなどして、AIが出した情報が正しいかどうか確かめましょう。
今回の「バイブコーディング」でアプリを生成した開発者の場合なら、セキュリティ面に問題はないか、コードがわかる人やセキュリティの専門家に必ずチェックしてもらうべきでしょう。
特にセキュリティという分野の広さと、その変化の速さは独学では難しく、例えコーディングのプロであってもセキュリティに関してはまた別の話。
アプリを使う前に5つのチェック ポイント

アプリって、本当に便利ですが、セキュリティ対策がちゃんとしていないアプリを使っちゃうと、あなたの個人情報が漏れたり、不正にアクセスされたりする危険があるんです。
それが意図的であってもなくても可能性はゼロじゃない。
ですから、アプリやサービスを使うときは、それが「信頼できるものか」「安全対策ができているか」をよく確認することが大事。
大切なあなたの情報を守るために、ぜひ次のポイントに気をつけてみてくださいね。
1️⃣どこの誰が作ったアプリか、ちゃんと確認してね
アプリやサービスは、誰が開発して提供しているのか、必ずチェックしましょう。
特に、個人が作った無料アプリとか、会社の情報がほとんど載ってないサービスには、注意が必要。
「怪しいな」って思ったら、ちょっと立ち止まって考えてみてくださいね。
2️⃣みんなのレビューや評判を隅々までチェック!
アプリストアとかウェブサイトにある、実際に使ってる人のレビューや評価を、しっかり見てみましょう。
「なんか変な動きをする」「個人情報を勝手に集めてるって報告がある」「すぐ止まる」といった情報がないか確認してみてください。
ポジティブな口コミよりネガティブな口コミをチェック。
ネガティブな口コミについては、ただの誹謗中傷ではなく「具体的な内容」かどうかも確認しましょう。
3️⃣求められる「権限」に注意! 安易に情報を入力しない
アプリをインストールするときって、「連絡先へのアクセス」「位置情報」「マイクへのアクセス」「カメラへのアクセス」とか、いろいろな「権限」を求められますよね。
そのアプリの機能から考えて「こんなに権限いる?」ってくらい多くを要求していないか、必ず確認してください。
もし、機能とは関係ないような権限まで求めてきたら、それは危険なサインかも。
少しでも「おかしいな」「なんか怪しいな」って感じたら、そのアプリやウェブサイトに、大切な個人情報を入力したり、ファイルをダウンロードしたりするのは絶対にやめましょう。
4️⃣スマホやPC、セキュリティソフトはいつも最新の状態に!
あなたが使っているパソコンやスマホのOS(基本ソフト)、それからセキュリティソフトは、常に最新の状態にアップデートしておくのが鉄則です!
こうしておけば、発見されたばかりのセキュリティの弱点(脆弱性って言います)が直されて、怪しいアプリとかファイルを見つけたり、ブロックしたりできる可能性が高まりますからね。
こまめなアップデートは、あなたのデジタルライフを守るための基本中の基本ですよ。
5️⃣「簡単」「誰でも」って言葉にダマされないで!
「開発が簡単だからといって、そのサービスが安全とは限りません。」これは私が一番伝えたいことです!
長年詐欺を追いかけてきた私から言わせれば、どんなサービスにも共通して言えることでもあります。
「絶対に安全!」なんてものは、この世にはないと思ってくださいね。
提供元が信頼できるか、使ってる人の評判はどうか。
そして「これって、本当に安全に作られてるのかな?」っていう疑いの目を常に持つこと。
これこそが、あなたの身を守る上で、何より大事なことになりますから、ぜひ心に留めておいてくださいね。
AIの時代も、大切なあなたの情報を守り抜こう!
AIって、私たちの生活や仕事を、本当に便利で豊かなものにしてくれる、素晴らしい技術です。
でも、その「簡単さ」の裏に隠れているリスク、特に今回取り上げた「バイブコーディング」のような開発手法が引き起こすセキュリティ上のリスクを理解しておくことが、これからの時代には欠かせません。
アプリの目に見える機能や便利さだけじゃなくて、そのサービスが「どれくらい安全か」っていう視点も持つ習慣をつけましょう。
アプリの提供元をしっかり確認して、個人情報の安易な入力を避けて、いつも「これ、安全かな?」って自問自答する姿勢を持つことが、AI時代のデジタル社会で詐欺からあなたの情報を守るための、一番効果的な対策になるはずですよ!
今回の情報が、皆さんのデジタルライフの安全に役立つことを願っています。
関連記事

@csrf_exemptが招くCSRF攻撃の本当の怖さ AIの提案を信じた結果
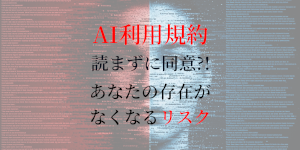
AI利用規約を読まずに同意しては危険!あなたの存在がなくなるかも
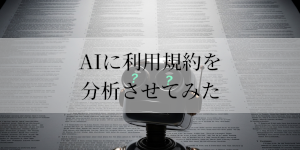
AIに利用規約を分析させてみた!GeminiとChatGPTの違いと自衛術
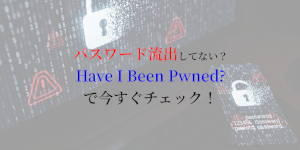
パスワード流出してない?Have I Been Pwned?で今すぐ確認!無料で使える情報漏洩チェックツール
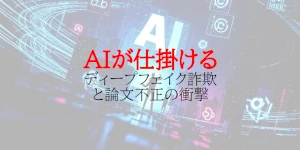
見抜けるか?AIが仕掛けるディープフェイク詐欺と論文不正の衝撃

AIの光と影 Geminiが拓く可能性と潜むリスク
